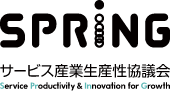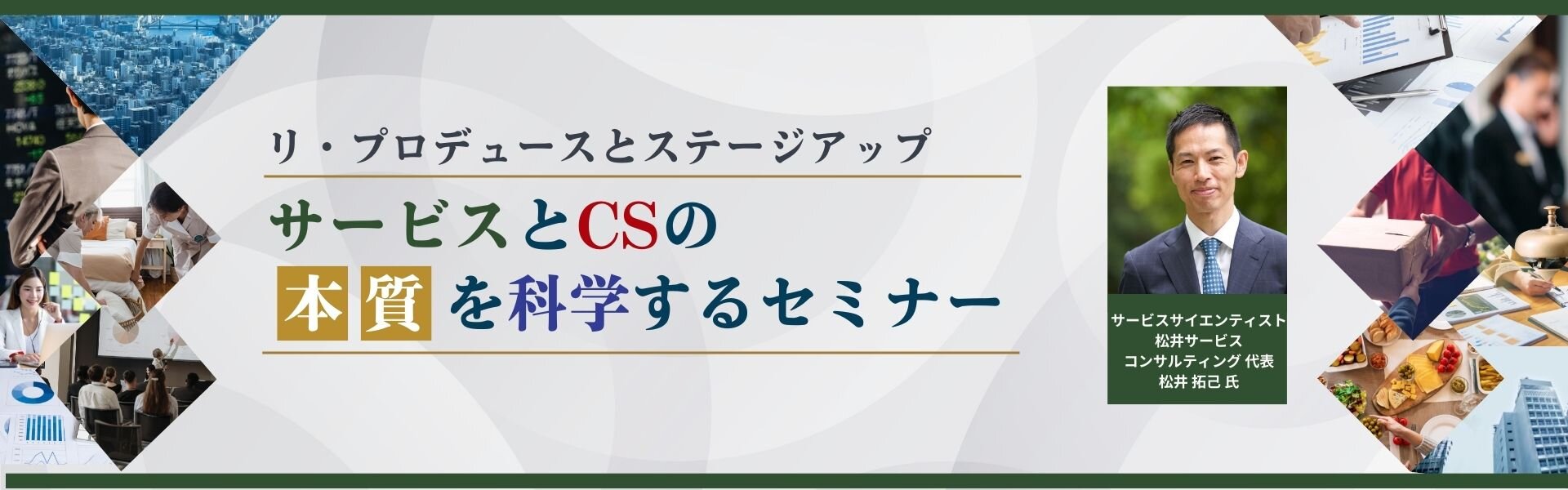【連載】CS向上を科学する【CS向上を科学する:第124回】サービスを「リ・プロデュース」する!公開日:2025.04.02
松井サービスコンサルティング
代表/サービス改革コンサルタント
松井 拓己


みなさんこんにちは。サービスサイエンティストの松井拓己です。2014年から当連載が始まって10年が経ちました。楽しみにしてくださっている読者の皆さん、つまみ食いでも参考にしていただいた皆さん、いつもご愛読いただいてありがとうございます。
連載を始めたころは、目に見えない「サービス」や「CS」の本質論をお伝えすることで、属人的な経験やセンスに頼り切るのではなく、組織的で納得感と成果実感のある取り組みを強化したい。そんな思いがありました。その思いと本質論は、今でもブレていません。
一方で、この「サービスの科学」を活用する企業のテーマや取り組み方は、この10年で進化してきました。もちろん今でも、顧客の事前期待の的をモデル化して、サービスの価値を高めたり、進化を加速したり、新サービスを開発したり、成果直結型CSにステージアップしたり、サービス品質向上をテコ入れしたりと、こういった取り組みに活用いただいています。最近では、前回取り上げたように、異業種の成功事例をサービスモデルの観点で分析してヒントを得る「サービスモデルマーケティング」を取り入れる企業も増えました。さらには、「顧客の」ではなく「従業員の事前期待」をモデル化して、育成や活躍、採用活動を設計する取り組みも始まっています。
継続は力になっているのか?
活用の幅が広がったことで、見えてきたことがあります。「継続は力なり」という言葉がありますよね。サービスやCSに関する取り組みは、「もう長く継続しています」という会社が多くあります。その継続は、力になっていますか?継続すれば自動的に力になるのではありません。実際に、「長年続けているけれど成果が出なくてマンネリ化している」とか、「同じような活動が、何度も立ち上がっては消えていく」という悩みをよく伺います。力になるように継続している会社と、継続しているだけの会社の差は、時間と共に広がっていきます。継続を力に変えるのがうまい会社が行っているのが、「リ・プロデュース」です。文字通り、サービスやCSを「もう一回」プロデュースすることです。
成長の足掛かりは「リ・プロデュース」
1回目のプロデュースは、サービスを開発したときや、CSの活動を立ち上げたときのことです。この時には、事業シナリオやビジネスモデル、そしてサービスモデルを、時間をかけて丁寧に設計したはずです。そして実際に立ち上がってから今日まで、皆さんの知恵と工夫でサービスの価値を育ててきました。失点が随分減って、顧客は高い評価をしてくれるようになってきたのではないでしょうか。今、皆さんのサービスは、顧客にとってどんな価値があるのでしょうか?それをどうやって生み出しているのでしょうか?それをモデル化できれば、価値を生みだす精度が向上します。組織での再現性も向上します。こうしてレベルの高いところで価値が安定すれば、それを「足掛かり」にして、さらなる成長や進化への挑戦を上乗せできるでしょう。その挑戦で得た経験知をモデル化すれば、新たな「足掛かり」になります。これを繰り返すことで、着実に成長の階段を登っていける。まさに「継続が力になる」わけです。
逆にリ・プロデュースができなければ、個人の経験値が高まっても、組織的なサービスレベル向上は限定的でしょう。結局、各自の経験とセンスでできる範囲が、価値向上や進化の「限界ライン」になってしまいます。これまで育て上げてきたサービスやCSを次のステージに押し上げるために、皆さん自身の手でサービスをリ・プロデュース(もう一回、プロデュース)するのです。
「サービス・リ・プロデューサー」の育成も始まっています。実際のネーミングは各社で工夫されていて、私と同じ「サービス・サイエンティスト」であったり、「バリュー・コ・クリエイター」としている企業もあります。実際の役割は、当連載で取り上げてきたサービスとCSの理論と手法を習得して、自社サービスをモデル化しながら価値向上や進化をガイドするスキルを持つ、まさにリ・プロデュースを担う人材です。サービスの人材育成は、「若手向け」ばかり充実しています。もちろん、サービスの本質を若いうちから理解しておけば、育成と活躍が加速します。この育成と活躍の加速は、ベテランやマネジメント人材にも必要です。「リ・プロデュース」のスキルは、ベテランやハイパフォーマー、マネジメント人材が身に付ければ、これまで培ってきた豊富な経験知をモデル化して、自身のパフォーマンス精度を高めるだけでなく、それを皆で実践すれば組織的なサービスレベルは向上します。部下や後輩に対して「経験を積みなさい」ではない育成の加速もできるでしょう。このように、自身の経験知を組織の力に変え、事業成長にもっと活かせるようになります。同時に、これまで経験やセンスで行ってきたことがモデル化でき、組織的な価値が安定すれば、ベテランやマネジメント人材自身も「次のチャレンジ」にステージアップできるようになります。事業も人材も伸ばす、サービス・リ・プロデュースをリスキリングするのです。
松井氏が講師を務めるイベント情報
「サービスとCSの本質を科学する」セミナー
~リ・プロデュースとステージアップ~(6/18(水)開催)
サービスやCSを「リ・プロデュース」し、新たな価値を生み出しませんか?
これまで築き上げてきたサービス事業やCS活動をステージアップするために、シンプルな理論と手法を用いて、付加価値型のサービスをモデル化します。また、取り組みの道しるべとして、6つの壁(顧客不在、建前、闇雲、実行、継続、情熱の壁)についてもお話します。
<筆者プロフィール>

松井 拓己
(Takumi Matsui)
松井サービスコンサルティング
代表
サービス改革コンサルタント
サービスサイエンティスト
サービス改革の専門家として、業種を問わず数々の企業の支援実績を有する。国や自治体、業界団体の支援や外部委員も兼務。サービスに関する講演や研修、記事連載、研究会のコーディネーターも務める。岐阜県出身。株式会社ブリヂストンで事業開発プロジェクトリーダー、ワクコンサルティング株式会社の副社長およびサービス改革チームリーダーに従事した後、松井サービスコンサルティングの代表を務める。
著書:価値共創のサービスイノベーション実践論(生産性出版)、日本の優れたサービス2~6つの壁を乗り越える変革力~(生産性出版) ほか
▼ホームページURL/サービスサイエンスのご紹介
http://www.service-kaikaku.jp/